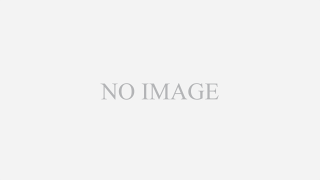映画『病院坂の首縊りの家』とは?
Amazonプライム・ビデオで鑑賞した市川崑監督の1979年の作品『病院坂の首縊りの家』。横溝正史原作の金田一耕助シリーズの最終作です。ホラーとミステリーに、市川崑らしいリズムと演出美が重なる、異空間的な映画体験となりました。
ミステリーなのに、クスッと笑える?コメディとの絶妙なバランス
一見、正統派の推理ドラマ。しかしこの作品には、不思議と笑える要素がところどころに存在しています。
草刈正雄演じる青年・黙太郎の軽快な立ち回りが、シリアスな空気を適度に和らげていました。
また、加藤武、小沢栄太郎、大滝秀治、小林昭二、三木のり平といった濃いベテラン俳優たちが、舞台演劇のような誇張気味の演技で画面に深みを与えていました。
一方で、佐久間良子(着物)や桜田淳子(洋服)といった女性陣の美しさも印象的。恐怖と華やかさが共存する、独特の作品世界がありました。
奈良・吉野の街と、廃墟の洋館のコントラスト
舞台は奈良県・吉野。シリーズ過去作のような秘境的な村ではなく、街の風景が多く登場します。それでも、洋館の廃墟だけは強烈に異質。
風鈴の音、坂道、写真館。どれも物語の中で象徴的に使われ、空気感を構成しています。
📸 写真、風鈴、坂道…すべてが“語る”映画。
特に印象に残ったのは写真。花嫁姿の写真が見せる恐怖、そして写真館の暗室で現像されるプロセスは、知らない時代のテクノロジーが「エモい」と感じるほどの臨場感でした。
正面と遠景の切り替えが生む、昭和的ビジュアルの魅力
人物が話すシーンでは、しっかり顔を捉えた正面撮りが多いのに対し、景色や坂道の場面ではぐっと引いた構図。
この構図の切り替えが、空間の広がりと閉塞を映し分けていて、まるで舞台美術のような設計を感じました。
🌿 遠景が映るたび、なんだかうれしくなる。
昭和映画の“ゆとりある視線”を感じた瞬間です。
音の演出に“昭和ホラー”のDNAを見る
音響もとても印象的でした。怖がらせるシーンでは、効果音が不自然なほどピタリとタイミングよく入るのです。
それが逆に“演出されてる”と分かるレベルで、不思議と安心感がありました。昭和のお化け屋敷のような懐かしい怖さ。
また、早口で説明セリフを話す女性に対して、カメラが高速でカットを割っていく演出は、市川崑らしい編集の遊び。
“情報の洪水”のような場面展開に、どこか今のオタク的なノリを感じました。
『シン・ゴジラ』との構造的な共通点
ふと頭をよぎったのが、庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』です。
政府関係者の早口会話劇が続く室内シーンと、ゴジラという“非現実”の対比。
この構造はまさに、市川崑監督が築いた手法にも通じる部分があります。
🎥 現実と異常が交錯する構造美。それが両監督に共通するDNAかもしれません。
まとめ:知らない時代に、懐かしさを感じる
金田一耕助シリーズの中でも、最終作にふさわしく密度の高い『病院坂の首縊りの家』。
恐怖・笑い・美しさ・過剰・過去。いくつもの要素が雑多に絡み合って、ひとつの世界を築いていました。
昭和という時代を知らなくても、なぜか“懐かしさ”を感じるのは、この映画が「時間」を丁寧に扱っているからかもしれません。