『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』、いや~、観終わったあと「すごかったな…」としばらく呆然としてしまいました。
あいかわらずの超絶アクション、古い映画へのリスペクト、そしてなんといっても今っぽいテーマ「AI」。それら全部を、ちゃんと“娯楽”の枠の中でやってのけてる感じが、さすがでした。
今回は、そんな本作の魅力を「アナログ推し」「映画愛」「AIへのひねり」なんてテーマで、ちょっとゆるめに語ってみたいと思います。
カギってなに?――正体はよくわからないけど超大事!

まず、今回のキーアイテム(まさに“鍵”)はその名も「カギ」。
だけど、このカギが具体的に何を開けるのか、何の役に立つのかは最後までよくわかりません。でもね、そういうところが逆に映画らしいんです。
観ている私たちは「カギが大事なんだな」って思って、それを奪ったり守ったりするイーサンたちを応援してる。
この「物語を前に進める装置としてのカギ」って、ちょっと前のシリーズに出てきた「ラビットフット」とか、ゲームの『キングダムハーツ』なんかとも似てます。
意味はあいまいでも、見た目が“物”として存在してるから、アクションがグッとリアルになる。そういう“物質的”な演出が、やっぱり映画って感じで好きなんですよね。
トムのガチアクションがすごすぎる

本作のいちばんの見どころは、やっぱりトム・クルーズの体当たりアクション。列車の屋根でのバトルとか、バイクで崖から飛ぶとか、あれほんとに本人がやってるって聞いたとき、ちょっと信じられなかったです。
しかも驚いたのが、あのバイクスタントを最初に撮ってるってこと。つまり「このアクションをやるために、あとから話を組み立てる」って制作スタイルなんですよ。
普通の映画づくりと逆なんですね。
このやり方って、無声映画時代の伝説の俳優バスター・キートンにすごく影響受けてるんだそう。確かに、全身で語る演技って、画面越しでも伝わってきます。
エンティティって、実はちょっとポンコツ?
今作の「敵」はAIの“エンティティ”。なんでもかんでも知ってて、全世界に潜伏してて、人間よりも賢い…っていう設定。でも、実際のところやってることって、
「ちょっと違う方向を指示して混乱させる」とか、「ミスリード情報をちょい漏らす」とか、思ったより地味だったりします(笑)。
観ながら「もっとすごいことできそうなのに?」と思った方もいるかもしれません。でも、ここもたぶんわざとなんです。
あえて現実のAIとはズレた、ちょっと“なんちゃってAI”感を出してくることで、「AIってそもそも何なの?」って問いを浮かび上がらせてる気がします。
今のAIって、実際には「予測」と「模倣」の塊。意思とか感情はないし、いきなり人類に反逆…なんてのは、かなりフィクション寄りな話。
でも、そういう“イメージとしてのAI”が社会の中で暴走したらどうなる?っていう視点は、ちょっとリアル。
物質で語るアクション映画の美学

この映画、何から何まで「本物」にこだわってるんですよね。爆発、列車、クラシックカー、崖、潜水艦、そしてトムの肉体……。全部、CGじゃなくて“そこにあるもの”で作ってる。
それって、すごく古典的なやり方でもあるけれど、だからこそグッとくる。目に見えるもの、耳で聞こえる音で感情を動かしてくるあたり、まさに映画の原点って感じ。
たとえばこんな作品へのオマージュが感じられました:
- 『スパイ大作戦』(シリーズの原点)
- バスター・キートンの『キートンの大列車追跡』
- 初期の『007』シリーズや『ナポレオン・ソロ』
- 『インディ・ジョーンズ』のアドベンチャー感
そしてカギという小道具も、やっぱり『キングダムハーツ』的な“象徴”としての使い方。何かを開けるというより、物語を動かすきっかけとしての存在感なんです。
まとめ:派手だけど、どこか懐かしい。
最先端の技術が当たり前になった今だからこそ、トム・クルーズはあえて逆を行く。本物のスタント、本物のロケ地、そして人間の「身体」で魅せる映画づくり。
それが観ているこちらの“心”を動かすんですよね。
そして、AIというちょっと不気味な存在を“ちょっとヘンでポンコツかも?”って感じで描くことで、「テクノロジーと人間、どう付き合っていく?」って問いもちゃんと残してくれる。
娯楽として面白くて、でも後からじわじわ効いてくる映画。まさに今だからこそ必要なアクション映画なんじゃないかなと思いました。トム・クルーズが飛び続ける限り、きっと私たちも、何度でも劇場に足を運んでしまいますね。

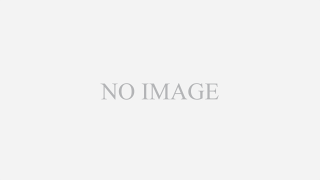
コメント